戦略グループとは、同一産業内に属する企業群が、その戦略等の違いにより活動するセグメントを棲み分けているという概念です。
これは元々、ハーバード大のマイケル・ハントが、アメリカ家電産業の競争について執筆した博士論文で提唱したもので、その内容は、家電産業に属する各企業を戦略方針・差別化・製品展開の幅・垂直統合の度合い・組織構造・コスト構造などの項目で分類すると複数のグループに集約でき、特に製品展開の幅と垂直統合の度合いという項目で分類すると4つの特徴のあるグループに集約できるというものでした。
この概念を援用し発展させたのがポーターで、同一産業内に属する各企業を、垂直統合の度合い・品質など14の項目を使ってそれぞれ2次元マトリクスでマッピングし、最も特徴のある組み合わせのマップが戦略グループになるという「戦略グループマップ」という分析方法を提唱しました。また、彼は3つの基本戦略が同一産業内で有効になる要因として戦略グループと移動障壁があり、各グループ間に移動障壁があるので3つの基本戦略を取る企業ごとに棲み分けが可能になるとしました。(それは同時に、3つの基本戦略を各企業がとるので戦略グループが形成されるとも言えます。)。このポーターの指摘の通り、戦略グループを考えるうえで重要になるのが「移動障壁」という概念です。移動障壁とは、ある戦略グループから別の戦略グループに参入する際に、それを阻害する何らかの要因のことを言います。その要因として下記があげられます。
1.競合に由来する要因
・進出したいグループに既に強固なブランディングを構築している競合がいる。
・競合が「このセグメントでは絶対に他社に負けない」と日頃から牽制している(=シグナリングと言います。)。
・競合企業の人脈・政治力・契約などにより原材料供給業者・物流業者・販路が占有されている。
2.戦略グループが属するセグメントに由来する要因
・特殊な技能や許認可免許を必要とするセグメントである。
・すでにセグメントのパイが一杯で参入の余地がない。
・大規模な投資(製品のフルラインナップや事業の垂直統合、非常に高額な設備投資など)を必要とするセグメントである。
・顧客に高いスイッチングコストがある。
3.自社に由来する要因
・戦略的要因
これまでの戦略を変更するのが困難(マーケティングの5Pの変更等様々)。
・経済的要因
コスト構造が大幅に変わる。
財務が大きな影響を受ける。
・組織的要因
組織構造や管理方法の変更に伴う混乱が大きい。
人材の再教育や新規採用に時間とコストがかかる。
以上が戦略グループと移動障壁の大まかな内容です。ちなみに戦略グループについて石井他は戦略グループは事業の広がりの差異で分類できるとし、移動障壁については経済・組織・戦略的障壁があるとしています。では次に、なぜ戦略グループと移動障壁が重要なのかを考えてみましょう。
まず戦略グループについては、自社の競合企業をより明確に判別できるからです。同業種であっても戦略グループが違っていれば、ターゲット顧客やビジネスモデルが違うので直接の競合にはならず、よって自社の脅威になりません。脅威にならないという事は、競合として逐一チェックする必要がないので、その分、リサーチの負担が減ります。また、ライバル関係にないので協力関係になる可能性もあります(例えばトヨタ自動車とダイハツ工業は普通車と軽自動車とで棲み分けていますが、資本関係でみると協調関係になっています。)。ですが注意しないといけないのは、イノベーションのジレンマで有名なクリステンセンなどが指摘している様に、既存の戦略グループでは考えもつかなかったような付加価値を持って別の戦略グループから参入しビジネスモデルが書き換えられる可能性があることです。特に業界内のビジネスモデルがマンネリ気味であった場合にはその傾向があり、新たな付加価値を携えていきなり参入してくるので注意する必要があります。
次に移動障壁ですが、自社が属する戦略グループが他の戦略グループと比較して移動障壁が低い場合、参入される恐れがあるので注意する必要があります。基本同業種なのでシナジーを発揮しやすく、新規創業者や他業種業者よりも容易に参入されやすいです。恐らく真っ先に参入するのが同業者になるでしょう(もちろん、地域の同業者間で縄張りを荒らさないという暗黙のルールがあればこの限りではありませんが。)。よって移動障壁を上げるために、上記した移動障壁の要因を構築して参入を阻止する必要があります。
ではここで、とある地域の宅配弁当業界を例に、戦略グループと移動障壁の内容を簡単に考えてみましょう。
A地域は中小の工場が多い地域で、昼間人口はこの10年で増加しているものの夜間人口は激減している。飲食店や小売店は減少気味だが、宅配弁当業者は昼間人口の増加に沿うように増加してきており現在は100店舗あって、このうち92店舗がよくある宅配弁当の個人事業主、3店舗が高品質をウリにしている店舗、残り5店舗が宅配サービスのある大手弁当小売チェーン店である。
92店舗の個人事業主は、配達地域は店舗によって様々であるが、多くは店舗周辺の地域をカバーしている。メニューは多種多様で価格帯は普通だが、業者ごとに微細な差異がある。個人事業主が多いのでフットワークの軽さや人脈営業によって顧客を得ており、主要顧客は地元企業や個人宅など注文があればどこでも行く。受注は前日15:00までで翌日に製造完了後、配達している。
次に高品質をウリにしている店舗は、宅配弁当とは別に強力な本業があり(広域に名の知れた鮮魚店や精肉店など)、本業の強みを活かした弁当をウリにしている(例えば「創業○年の目利き鮮魚店が作る『朝獲れ鮮魚の海鮮弁当』」など。)。メニューは絞られており価格帯は高いものの積極的な宣伝により品質重視の固定客が多い。仕入は本業で調達している。受注は当日の10:00までで昼に配達しているが、配達地域は本業の配達を優先しなければならないという制約があるため、その販路上のみ配達している。
最後に大手弁当小売チェーン店は、店舗販売以外に1,000円以上の注文時にのみ配達を行う。配達エリアは全域でメニューは多種多様、価格帯も普通である。仕入は本部から半加工の食材が送られてきて店舗内で製造している。受注は随時で受注後約30分で配達している。大手チェーンなので知名度はある。
このような事例の場合、戦略グループで分類すると、それぞれ順番に①時間集中のグループ、②高品質・販路限定のグループ、③全方位のグループ、と分けられるでしょう。次に移動障壁の内容を考えると・・・、
①⇒②の場合の移動障壁
・商品品質、ブランディングといった点で比較劣位にあり移動障壁が高い。
・仕入について②は本業から安く仕入れている可能性があるのでコスト構造でも劣位にあり移動障壁が高い。
①⇒③の場合の移動障壁
・商品展開、価格帯、販路が同質なので移動障壁が低い。
・③は大手なので、知名度、仕入や製造コストで障壁が高い。
・配達時間と受注時間で劣位にあり障壁が高い。
・昼以外の配達を行うと労働コストが増加するので障壁が高い。
②⇒①の場合の移動障壁
・販路を広げると本業の配達が遅延する恐れがある。配送人員を増加させた際には教育時間や支払賃金が増えるので障壁がある。
・普通の価格帯にすることで既存販路でのブランドが傷つく。
・販売数と原価率が変わらないと仮定した際に売上額・利益額が減少する。
②⇒③の場合の移動障壁
・②⇒①の場合の移動障壁と同様。
③⇒①の場合の移動障壁
・個人事業主のように顧客ニーズに柔軟な対応が出来ない。
・競争がし烈になる恐れがある
③⇒②の場合の移動障壁
・高品質な商品とブランディング
・・・他にもあるでしょうが、とりあえず上記が考えられますよね。注目してほしいのは、どの場合でも違った形で移動障壁が存在していることです。このように移動障壁は戦略グループごとに内容が異なるのが特徴です。そして、高い障壁がある場合には参入に失敗する可能性が高いので控えるべきですし、低いからと言って安易に参入すると、競争がし烈になり共倒れになる可能性があるので控えるべきです。
ただ、注意してほしいのは、移動障壁があるからと言って参入を諦めなければならない訳ではありません。例えば①が②に参入する際には、①は②に属するある企業と契約して②が本業で仕入れた獲れたて鮮魚を購入し、その販路外で「あの老舗鮮魚店が監修した『朝獲れ鮮魚の海鮮弁当』」を販売するという戦略が考えられます。パートナー企業とは棲み分けつつ、実質②の戦略グループに参入するのです。
また、移動障壁以外に戦略グループ間の相互関係も考える必要もあります。例えば、③⇒①への移動は商品展開など類似点が多いので一見すると容易なようですが、①と③が棲み分けられている理由を考えると、もしかしたら昼配達の需要が多いので①が獲りこぼした客を③が獲ているのかもしれません。この場合、消費者は③よりも①のメニューに魅力を感じているが、何らかの理由により注文できないので仕方なく③に発注しているのかもしれません。もしそうならば、①をつぶす戦略をとると、③に魅力を感じない消費者は家で弁当をつくって持参するようになりこの地域の宅配弁当業界のパイ自体が縮小する恐れがあります。チェーン店の弁当に魅力を感じない消費者が多い地域では自殺行為になります。
自社が属する戦略グループ外に参入する際には、移動障壁の程度と、グループ間の相互関係も考えて実施しましょう。

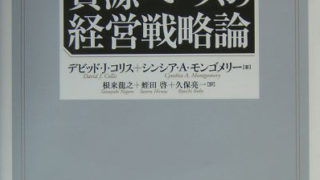


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/130b028b.243604f9.130b028c.721b2f8b/?me_id=1213310&item_id=18076366&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9119%2F9784776209119.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9119%2F9784776209119.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)